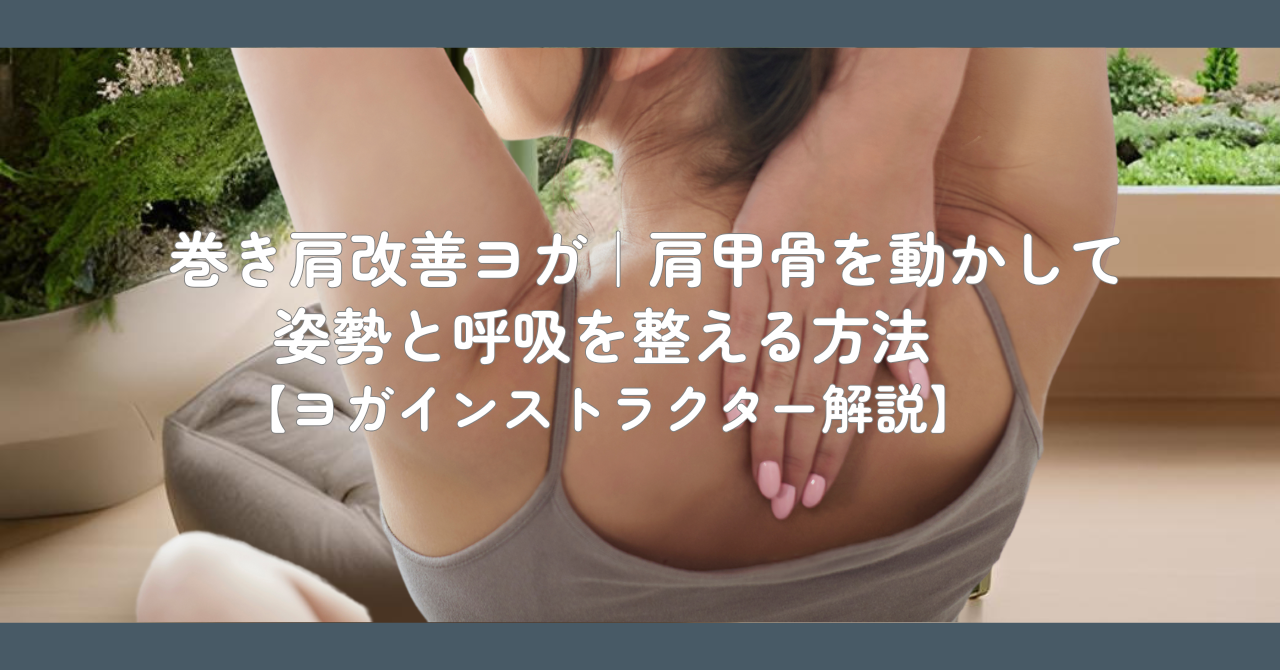「肩が内に入る」「呼吸が浅い」──それ、巻き肩かもしれません
「背筋を伸ばそう」と意識しているのに、
なんだか肩が内に入り、胸が縮こまってしまう……。
そんな感覚、ありませんか?
あるいは、ふと鏡に映った自分の姿を見て、
「あれ?前よりも姿勢が丸くなってるかも」と感じたことはないでしょうか。
それはもしかすると、巻き肩のサインかもしれません。
巻き肩とは、肩が前方に巻き込むように内側へ入り、
本来の正しい位置からずれてしまっている状態です。
この姿勢が続くと、肩まわりの筋肉が硬くなってしまい、
- 胸が縮こまり呼吸が浅くなる
- 首や背中が張りやすくなる
- 二の腕が前に出て見えることでスタイルが崩れて見える
など、さまざまな不調や見た目の変化を引き起こすことがあります。
特に、40代以降になると筋力や柔軟性のバランスが変化し、
「猫背っぽくなってきた」「呼吸が浅くなってる」と感じる方が増えてきます。
でも、巻き肩も“クセ”であることが多いため、
正しい体の使い方を少しずつ身につけていくことで、
ゆっくりでも、確実に変えていくことができます。
このブログでは、
- 巻き肩が起こる仕組み
- 肩甲骨の正しい動かし方
- ヨガを通じて巻き肩を改善する具体的なポーズ
- 体の使い方と日常での意識のコツ
を、ヨガインストラクターの視点でお伝えしていきます。
「肩が自由に動くって、こんなに心地いいんだ」
そう感じられるような体との出会いを、あなたにも体験してほしい。
巻き肩改善の先には、
自分らしく動き、暮らしを楽しめる体がきっと待っています。
さあ、まずは自分の肩と向き合う時間から始めてみましょう。
📚目次|巻き肩にさようなら。肩甲骨を動かすヨガ
- 巻き肩とは?肩甲骨が動かなくなる理由
- 巻き肩がもたらす体の不調と悪循環
- あなたは大丈夫?巻き肩セルフチェック
- 肩甲骨を正しく動かすために知っておきたいこと
4-1. 肩甲骨の役割と構造
4-2. 肩甲骨と肋骨・背骨の連動
4-3. 呼吸や骨盤とのつながり - 巻き肩改善に効果的なヨガポーズ3選
5-1. 背中で合掌のポーズ(肩を開く)
5-2. 四つんばい+胸開きストレッチ
5-3. ワニのポーズ(胸郭と肩甲骨の連動) - レッスンで見えてきた変化|生徒さんたちの声
- よくある質問|巻き肩を改善するための注意点と生活習慣
まとめ|肩甲骨を動かし、自分らしく整う体へ
1. 巻き肩とは?肩甲骨が動かなくなる理由
巻き肩とは、肩が内側に巻き込むように前へ出てしまい、
肩甲骨が本来の位置から外れている状態のことをいいます。
この姿勢が続くと、肩甲骨の動きが制限されて、
背中や首まわりに余計な力が入りやすくなってしまいます。
見た目としても、胸が縮こまったり、猫背になっていたり、
なんとなく“元気がないように”見えてしまうこともあるかもしれません。
巻き肩の一番の原因は、日常の“クセ”かもしれません
巻き肩は、特別な動きが原因で起こるというよりも、
日々の暮らしの中で少しずつ染みついていく「クセ」から始まることが多いようです。
たとえば…
- スマホを見るとき、つい肩が前に出てしまう
- パソコン作業で、知らず知らず肩がすくんでいる
- バッグをいつも片側の肩で持っている
こういった動きが毎日続いていると、
体はそれを“当たり前の姿勢”として覚えてしまい、
肩まわりや背中の筋肉に偏った使い方がクセづいてしまうようになります。
肩甲骨は“背中で浮かぶ羽根”のような存在です
肩甲骨は、背中に左右一枚ずつある“浮いている骨”です。
筋肉によって肋骨の上に浮かぶように支えられていて、
本来はとても自由に動ける構造をしています。
この肩甲骨は、
- 腕を自由に動かす
- 呼吸を助ける
- 姿勢の安定をサポートする
といった大切な役割をもっています。
でも巻き肩になると、肩甲骨は外側へ引っ張られていき、
背中の筋肉が引き伸ばされたまま硬くなり、
一方で胸の筋肉は縮んでしまった状態で固まっていきます。
その結果、肩甲骨が“滑るように動く”という本来のしなやかな働きが失われて、
動かしづらさやコリ、痛みにつながってしまうこともあるようです。
巻き肩の怖さは、“感覚が鈍くなること”かもしれません
巻き肩が習慣になると、自分では「まっすぐ立っている」と思っていても、
実際には肩が内に入り、背中が丸まり、胸が縮こまっている……
そんな姿勢になってしまっていることが少なくありません。
つまり、**「自分がどんな姿勢をしているのか、わからなくなってしまう」**ことがあるのです。
でも大丈夫です。
ヨガでは、そんな“体の感覚のズレ”を少しずつほどいていきながら、
本来の動きや感覚を取り戻していく練習ができます。
次の章では、巻き肩によって引き起こされやすい体の不調や、
それがどう悪循環につながってしまうのか──
一緒にみていきましょうね。

2. 巻き肩がもたらす体の不調と悪循環
巻き肩は、見た目の姿勢だけでなく、
体の内側にもさまざまな影響を与えると言われています。
はじめのうちは「少し肩が前に出てるかも?」という程度でも、
そのまま放っておくと、知らないうちに
呼吸の浅さや肩こり、疲れやすさへとつながっていくと感じる方も多いようです。
肩の位置が変わると、呼吸も浅くなりやすい
巻き肩になると、胸が内側に閉じてしまい、
自然と呼吸が浅くなります。
実際、「深く息が吸えない」と感じている方の中には、
姿勢の崩れが原因になっているケースも少なくありません。
胸のスペースが縮こまり、肺が広がりにくくなると、
息が十分に入らず、呼吸が浅く・早くなると感じる方も多いようです。
呼吸が浅い状態が続くことで、
- 気づかないうちに体が緊張しやすくなる
- 自律神経が乱れやすくなる
- 睡眠の質が落ちる
といった変化を感じている方もいらっしゃいます。
肩甲骨が動かないと、首や背中に負担がかかりやすくなります
本来、肩甲骨は「浮いた骨」で、背中を自由に滑るように動いています。
でも巻き肩の状態が続くと、
肩甲骨が背中の外側に引っ張られてしまい、動きがどんどん小さくなっていきます。
その結果、腕を動かすときに本来なら肩甲骨が分担するはずの動きを、
首や背中の筋肉が代わりにがんばってしまう状態になります。
そうなると、
- 首の後ろが張る
- 肩がずっと重だるい
- 背中が硬くて痛みやすい
といった不調を感じている方もいらっしゃいます。
「マッサージに行ってもすぐに元に戻ってしまう」
という方は、肩甲骨の動きがうまくいっていない可能性があるかもしれません。
さらに、気づかない悪循環が生まれてしまうことも
巻き肩による不調が続くと、
体はさらに「守るような姿勢」になってしまいがちです。
呼吸が浅い → 肩がこる → 姿勢が崩れる → 動きたくなくなる → 筋力が落ちる…
こんなふうに、知らない間に動きにくさのループに入ってしまうこともあります。
でも、だからこそ。
今、体の声に気づけたこのタイミングは、とても大切な分岐点になってくれます。
体は、どんな年齢からでも変わっていくことができるし、
少しずつでも、本来のしなやかさを取り戻していける力をもっているんですね。
次の章では、ご自身の巻き肩の状態をやさしくチェックできる
「セルフチェック法」についてお伝えしていきますね。
ふだんの姿勢に、ちょっとだけ意識を向ける時間をつくってみましょう🌿

3. あなたは大丈夫?巻き肩セルフチェック
「姿勢に気をつけているつもりなのに、なんだか肩が前に出て見える…」
「写真に写った自分の姿に驚いたことがある」
そんな経験はありませんか?
実は、自分では気づかないうちに巻き肩になっているという方はとても多く、
まずは現在の状態を知ることが改善の第一歩になります。
ここでは、ご自宅で簡単にできるセルフチェック法をご紹介します。
姿勢を無理に直す前に、まず“今の自分”とやさしく向き合ってみましょう🌿
✅ 巻き肩セルフチェック|壁を使ったチェック法
【チェック方法】
- 壁に背を向けて立ちます。
- 頭・背中・お尻・かかとを壁につけて、自然に立ちます。
- そのままの状態で「両肩」と「手の甲」が壁につくかを確認します。
【結果の見方】
- 肩と手の甲が壁につく → 巻き肩の可能性は低め
- 肩や手の甲が壁から浮く → 巻き肩傾向があるかもしれません
ポイントは、“無理に胸を張らないこと”。
あくまで自然に立った状態で行ってくださいね。
✅ 巻き肩セルフチェック|仰向けチェック法
【チェック方法】
- 床に仰向けに寝ます(ヨガマットや布団の上でもOK)
- 両足を軽く開き、手のひらを上にして体の横に置きます
- 力を抜いて、両肩が床につくかを確認してみましょう
【結果の見方】
- 肩が自然に床に触れている → 正しい位置に近い状態
- 肩が浮く・背中の上部が浮く → 肩が内側に巻かれている可能性があります
特に「床に寝ると背中や肩が浮いてしまう」方は、
日常的に胸の筋肉が縮み、肩甲骨が広がった状態になっていることもあります。
✅ こんな感覚、ありませんか?|巻き肩チェックのサイン
- 上半身をリラックスさせて立つと、手の甲が前を向いている
- 両腕をまっすぐ上げるのがつらい
- 背中を反らせるより、丸める方がラクに感じる
- 肩こりが慢性的に続いている
- 猫背になっていると周囲に言われたことがある
これらのうち、いくつか心当たりがある方は、
巻き肩の傾向があるかもしれません。
ただ、どれも「だから悪い」というわけではありません。
あくまで、**“今の体の状態を知るヒント”**として、そっと気づいていただけたらと思います。
💡大切なのは、「否定しないこと」
ヨガでは、今の体を否定するのではなく、
「そうなっているんだな」「気づけたことが大切なんだな」
と、やさしく受けとめることを大事にしています。
巻き肩も、知らないうちに身についた“体の習慣”のひとつです。
気づいたその瞬間から、整えるためのステップは始まっていきます。
次の章では、
肩甲骨を正しく動かすために大切な体のしくみや使い方を、
ヨガインストラクターの視点で詳しくお伝えしていきますね。
焦らず、少しずつ。
体の感覚を育てる時間を楽しんでいきましょう🌿

4. 肩甲骨を正しく動かすために知っておきたいこと
「巻き肩をなおしたい」「肩こりを楽にしたい」──
そう思ったとき、多くの方が“ストレッチ”や“筋トレ”を試されるかもしれません。
でも、肩甲骨を本来の位置に戻し、スムーズに動かせるようになるためには、
“体の仕組み”と“感覚”を理解することがとても大切になってきます。
この章では、肩甲骨を正しく動かすために、知っておきたいポイントを3つに分けてお伝えしていきます。
4-1. 肩甲骨は「浮かんでいる骨」|だからこそ影響を受けやすい
肩甲骨は、肋骨の上に“ただ乗っているだけ”の骨で、
関節でしっかり固定されているわけではありません。
だからこそ、
- 背中の筋肉
- 腕や肩まわりの筋肉
- 胸(大胸筋・小胸筋)
といった周囲の筋肉の影響をダイレクトに受けてしまうんですね。
ちょっとした筋肉のアンバランスや姿勢のクセでも、
肩甲骨の位置はずれてしまいやすく、
そこから「巻き肩」「肩こり」「動かしづらさ」などが生まれてきます。
4-2. 肩甲骨は“背骨・肋骨・骨盤”とつながっています
肩甲骨は単独で動いているわけではなく、
実は背骨や肋骨、骨盤と深くつながりながら連動しています。
たとえば:
- 背骨が丸まっていると、肩甲骨は外に引っ張られる
- 肋骨が硬いと、肩甲骨が背中を滑るように動けない
- 骨盤が後傾していると、胸が閉じて肩が前に出やすくなる
このように、体の中心にある軸(骨盤や背骨)が整っていないと、
いくら肩甲骨だけを動かしても、根本からの改善にはつながりにくいんです。
4-3. 呼吸と肩甲骨も、実は深くつながっています
巻き肩の方の多くに共通するのが、呼吸が浅いということ。
その背景には、「肋骨の動きの制限」や「横隔膜の働きの低下」があることも。
深い呼吸をするには、肋骨がしなやかに広がる必要があり、
そのためには背中や肩甲骨まわりの柔らかさが欠かせません。
また、呼吸によって動く横隔膜と骨盤底筋は、
体幹の深層でつながっているため、
肩甲骨を正しく動かすには、“呼吸の質”を高めることも鍵となってきます。
💡「肩甲骨だけを動かそう」としないことが、大切な一歩です
肩甲骨が自由に動くためには、
- 骨盤の安定
- 背骨のしなやかさ
- 肋骨の広がり
- 呼吸の深さ
こうした“全体のバランス”を整えることが、とても大切です。
ヨガでは、「一部だけに意識を向ける」のではなく、
体のつながりを感じながら整えていくアプローチを大切にしています。
次の章では、こうした「つながり」を感じながら実践できる
巻き肩改善のためのヨガポーズを3つ、ご紹介していきますね。
体をほぐすだけでなく、“感覚を育てる”ポーズとして取り組んでみましょう🌿
5. 巻き肩改善に効果的なヨガポーズ3選
〜“感覚を育てる”ポーズで肩甲骨の動きを取り戻す〜
ここでは、巻き肩の改善をサポートする
ヨガの基本ポーズを3つご紹介します。
どのポーズも、単に肩を伸ばすだけでなく、
**「肩甲骨が自由に動く感覚」「胸が開く心地よさ」**を取り戻すことを目指しています。
初めての方でも無理なくできる内容ですので、
ぜひ呼吸とともに、やさしく体を動かしてみてくださいね。
5-1. 背中で合掌のポーズ(肩まわりの深部を開く)
【効果】
- 肩甲骨まわりをほぐす
- 胸の筋肉(大胸筋・小胸筋)をゆるめる
- 呼吸が入りやすい姿勢をサポート
【やり方】
- 背筋を伸ばして立つか、あぐらで座ります。
- 背中側で手のひら同士を合わせて、合掌の形にします(無理な場合は、手の甲を合わせるだけでもOK)。
- 手を少しずつ上に引き上げて、肩甲骨を中央に寄せるような意識を持ちましょう。
- 3〜5呼吸ほどキープします。
【ポイント】
- 肘をできるだけ外に開いて、胸をやさしく広げるように
- 手が合わせづらい場合は、ストラップやタオルを使ってもOK
- 痛みがある場合はムリをせず、感覚を大切にしましょう
5-2. 四つんばい+胸開きストレッチ(背骨と肩甲骨の連動)
【効果】
- 胸椎(背骨の中央)と肩甲骨の連動を促す
- 胸郭の動きを広げる
- 猫背・巻き肩のバランスをリセット
【やり方】
- 四つんばいの姿勢をとります(肩の下に手首、股関節の下に膝)
- 右手を床につけたまま、左手をゆっくり天井方向へ開くように上げます
- 視線もゆっくりと上に向け、胸を広げる感覚を味わいます
- ゆっくり戻し、反対側も同様に行います
- 各側3〜5呼吸キープを目安に
【ポイント】
- 手の動きよりも「胸が広がる感覚」を優先に
- 骨盤は安定させ、背骨をやさしくねじるように
- 呼吸と連動する動きを意識してみてください
5-3. ワニのポーズ(胸郭と肩甲骨のつながりを取り戻す)
【効果】
- 肋骨と肩甲骨の動きをなめらかに
- 呼吸を深め、胸まわりの緊張をリリース
- 背骨のねじれを整える
【やり方】
- 仰向けになり、両膝をそろえて胸の方に引き寄せます
- 両膝を右側に倒し、左腕は真横に伸ばして肩の位置をキープ
- ゆっくりと視線を左に向け、背中全体をツイストさせます
- 左の肩甲骨が床につく意識で5呼吸ほどキープ
- ゆっくり戻り、反対側も同様に行います
【ポイント】
- 肩が浮く場合は、膝の位置を少し下げて調整してOK
- 深く呼吸をしながら、吸うたびに肋骨が広がる感覚を大切に
- 腰でねじらず、背骨全体をゆるやかに回旋させるイメージで
💡ポーズの効果を引き出すために|“感じながら動く”を大切に
ヨガのポーズは、**動きの「正しさ」だけでなく、「感覚を育てること」**がとても大切です。
「肩が少し軽くなった気がする」
「呼吸が深く入りやすくなった」
「胸の奥にスペースができたみたい」
そんな小さな変化に気づけることが、体が整い始めているサインかもしれません。
次の章では、マミヨガのレッスンを通じて見えてきた、
巻き肩改善にまつわる生徒さんのリアルな声をご紹介していきますね。
ご自身の変化のヒントになるようなエピソードがあるかもしれません🌷

6. レッスンで見えてきた変化|生徒さんたちの声
マミヨガでは、巻き肩や姿勢に関するお悩みを持つ方が通われています。
「猫背になってきた気がする」
「呼吸が浅くて、気づくと肩が力んでいる」
「肩甲骨が動いていないのが自分でもわかる」
そんな声とともにスタートする方がほとんどです。
でも、少しずつ体の感覚を育てていくうちに、
“あれ?”と気づくような変化が、そっと訪れるようになります。
ここでは、巻き肩をテーマにしたレッスンを通じて、
生徒さんたちからいただいた実際の声をご紹介しますね。
「呼吸がラクになってきた気がします」
はじめは、「深く吸おうとしても胸が動かない感じがする」とおっしゃっていた方。
胸のスペースを広げる動きや、肩甲骨の小さな動きからスタートし、
呼吸と動きをリンクさせる練習を続けていくうちに…
**「あ、今すごくスーッと息が入った気がします」**と、ある日ふとつぶやかれました。
自分の中で「変わった」と思う瞬間は、いつも突然やってきます。
そしてそれは、たいてい“がんばる”というよりも、“気づけた”ときなんですね。
「肩が軽くなった!って感じました」
ある生徒さんは、巻き肩によって肩甲骨が動かず、
常に肩まわりがガチガチで、マッサージに通い続けていたそうです。
でもレッスンで、「肩甲骨を意識して腕を動かす」練習を繰り返すうちに、
日常の中でもふとしたタイミングで、**「今、肩の力が抜けてる」**と感じられるようになったとお話しくださいました。
「この感覚がわかると、肩こりになる前に気づけるようになるんですね」
という言葉が、とても印象的でした。
「背中がスッとした姿勢でいるのがラクになってきました」
巻き肩の方にとって、「胸を張る=つらい」「背筋を伸ばす=疲れる」と感じることはめずらしくありません。
ある生徒さんも、「姿勢を正すと余計に肩が痛い」と悩んでいらっしゃいました。
でも、骨盤の位置や体幹とのつながりを意識したポーズを重ねていくうちに、
ご本人の言葉で、**「気がついたら、自然と姿勢が整ってきた気がします」**と感じられるように。
無理に形をつくるのではなく、
体の内側から整っていく感覚を味わえるようになったことが、
長く続けられる理由のひとつだと教えてくださいました。
💡 “気づく力”が育つと、体は自然に変わっていく
巻き肩の改善には、即効性があるわけではありません。
でも、続けていくうちに「肩のことを意識できるようになった」
「無理に直さなくても自然に整ってきた」と感じる方が多くいらっしゃいます。
マミヨガでは、
「正しい動きの中で、今どんな感覚があるか?」を大切にしています。
その“感覚”が育ってくると、体は自然に変わっていくものなんですね。
次の章では、
巻き肩を改善するためによくいただくご質問と、
日常生活でのちょっとしたコツをまとめてお伝えしていきますね。
ふだんの暮らしの中で、体にやさしい習慣を取り入れるヒントになれば嬉しいです🌱

7. よくある質問|巻き肩を改善するための注意点と生活習慣
巻き肩を整えていくうえで、レッスン中によくいただくご質問や、
日常で気をつけたいポイントをいくつかご紹介していきます。
「このままで大丈夫かな?」
「逆に痛めてしまわない?」
そんな不安を感じたときの参考になれば嬉しいです。
Q1. 背筋を伸ばすのがつらいのは、姿勢が悪いからですか?
「背筋を伸ばそうとすると、かえって肩や腰が疲れる…」
そんな声をよく耳にします。
でもそれは、単に“姿勢が悪い”からではなく、
体を支えるための深層の筋肉(体幹)がまだうまく働いていない状態かもしれません。
無理に背筋を伸ばすのではなく、まずは骨盤・背骨・肩の位置をやさしく整えていくことからはじめてみましょう。
呼吸に合わせて少しずつ整えていくうちに、自然とラクな姿勢が身についていくようになりますよ。
Q2. 「胸を張る」と言われると、肩が痛くなってしまいます…
「姿勢を正して、胸を張って!」と言われると、
つい肩甲骨をぎゅっと寄せて、肩が上がってしまう方も多いようです。
でも、胸を開く動きは**「無理に張る」のではなく、「広げるスペースをつくる」**ことが大切です。
マミヨガでは、肩甲骨の位置を整えながら、胸や肋骨まわりをゆるめて、
“内側から自然に広がる”ような感覚を大切にしています。
まずは「肩の力を抜く」「呼吸が入りやすい姿勢を探す」ことからはじめてみましょう🌿
Q3. デスクワーク中に気をつけることはありますか?
はい、長時間の座り姿勢は巻き肩を助長しやすいので、ちょっとした工夫が役に立ちます。
たとえば、
- 座面が少し高めになるようにクッションを敷く
- 骨盤を軽く立てるように意識する
- 肩に力が入っていないか、時々チェックする
- 1時間に1回、肩甲骨を寄せるような動きを取り入れる
こうした“小さな意識”の積み重ねが、姿勢に大きな変化をもたらしてくれます。
また、深く呼吸をするだけでも、自然と姿勢が整いやすくなるんですよ。
📌 マミヨガでは、デスクワークの合間にも取り入れやすい「椅子ヨガ10分クラス」も行っています。
呼吸を深めながら、肩まわりや背中をゆるめていく内容で、
「気軽にリセットできる時間」として、在宅ワークの方にもご好評いただいています。
💻 最新スケジュールやレッスン内容は、
▶ Instagram @mami.yoga.50 にてご案内しています。
ご興味があれば、ぜひチェックしてみてくださいね。
Q4. 巻き肩をなおすには、どのくらいの期間がかかりますか?
これもよく聞かれるご質問のひとつです。
巻き肩は“長年のクセ”によって少しずつ形づくられているもの。
その分、変化にも時間がかかることがありますが、“気づけたその瞬間”から体は変わりはじめます。
早い方で1〜2週間、じっくり取り組まれる方では数ヶ月かけて、
「気がついたら肩が軽くなってた」「自然と胸が広がってきた」と実感されることもあります。
焦らず、やさしく、自分のペースで向き合うことが、いちばんの近道なのかもしれません。
次の章では、
巻き肩を整えていく中で、どんな変化が起きていくのか?
そして、“一生動ける体”を育てるために、どんな視点が大切なのか?
最後に、これまでの内容をふりかえりながら、
体と心をやさしく整えていくためのヒントをお届けしていきますね🌿
自分の体と仲良くなる時間が、日常の中に少しずつ増えていきますように🌷

8. まとめ|肩甲骨を動かし、自分らしく整う体へ
巻き肩は、ほんの少しずつ積み重なった「姿勢のクセ」や「筋肉のアンバランス」が原因で、自分でも気づかないうちに定着してしまうことがあります。
呼吸が浅くなる
肩や首がこる
背中が丸まりやすい
姿勢が整わないことで、気分まで沈みがちになる…
こうした不調は、「年齢のせい」と片づけてしまいそうになるかもしれません。
でも、体はいつからでも、変わっていく力をもっています。
その鍵となるのが、肩甲骨のしなやかな動きなのです。
今回のブログでは、
- 巻き肩になるしくみ
- 自分の状態を知るセルフチェック
- 肩甲骨の動きを整えるために大切なこと
- 日常でも取り入れやすいヨガポーズ
をご紹介してきました。
どれも、強い力で矯正するのではなく、
**「体と対話するように整える」**ことを大切にした内容ばかりです。
マミヨガでは、
「正しい動きで感じること」
「感覚を育てながら、ケガをしない体をつくること」
を大切にしています。
がんばって姿勢を“つくる”のではなく、
体の内側から自然と“整っていく”ような変化を、
一緒に育てていけたら嬉しいです。
肩甲骨が動き出すと、呼吸もラクに、表情も明るく、
背中から気持ちもスッと立ち上がってくるような感覚に出会えるかもしれません。
そしてそれは、**「自分らしく動き、暮らしを楽しめる体」**へとつながっていきます。
今よりもほんの少し、肩の力を抜いて過ごせるように。
体と心の呼吸が、すこし深くなっていくように。
このブログが、そのきっかけになれば嬉しいです🌿
次回は、巻き肩とセットでお悩みの多い**「猫背・首のこり」**についてもご紹介予定です。
またぜひ、体と向き合う時間をご一緒できたら嬉しいです。
✅マミヨガの最新レッスン情報や椅子ヨガ動画はこちらから
▶ Instagram @mami.yoga.50